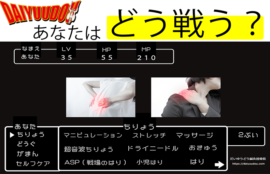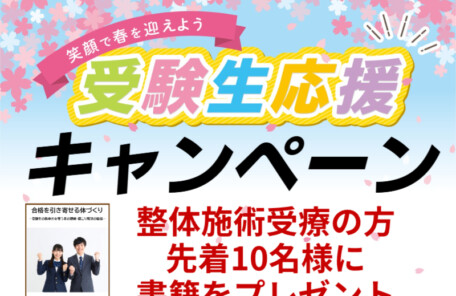第1回 秋から冬へ!冷えと寒暖差が邪魔をする寝つきの悪さ「入眠障害」とお灸でスムーズな眠りへ
「布団に入ってもなかなか眠れない」「考え事ばかりしてしまい時計ばかり見てしまう」といった、寝つきの悪さ(入眠障害)にお悩みではありませんか?
11月に入ると、私たちの体は季節の変わり目に特有の大きなストレスに直面します。これこそが、皆さんの快眠を遠ざける大きな原因かもしれません。
今回は、11月上旬から中旬にかけての気候が引き起こす入眠障害のメカニズムと、その対策として当院が行う箱灸(はこきゅう)が、腹部と腰仙部を温めることでどのようにスムーズな入眠を促すのかを詳しく解説します。
11月の気候が快眠を邪魔するメカニズム
寒暖差の拡大と自律神経のSOS
11月は、日中はまだ穏やかな暖かさが残る一方で、朝晩は一気に気温が下がり、日中と夜間の気温差(寒暖差)が非常に大きくなります。
私たちの体には、体温や血圧などを自動的にコントロールする自律神経が備わっています。
- 交感神経(アクセル) 活動時や緊張時に優位になる神経
- 副交感神経(ブレーキ) 休息時やリラックス時に優位になる神経
急激な寒暖差に対応しようとすると、自律神経は常に切り替えを強いられ、非常に疲弊します。これが「寒暖差疲労」と呼ばれる状態で、結果として自律神経のバランスが乱れてしまいます。
なぜ「寝つき」が悪くなるのか?
スムーズに眠りにつくためには、夜になると自然と副交感神経が優位になり、体と心がリラックスモードに入ることが必要です。このとき、手足など体の末端から熱を逃がし、体の深部の体温を下げることで、脳は「眠りの準備ができた」と判断します。
しかし、自律神経のバランスが乱れていると、以下の問題が起こり、寝つきが悪くなります。
- 交感神経の居座り 寒暖差疲労により、夜になっても「戦闘モード」の交感神経が優位なままとなり、脳や体が興奮状態から抜け出せず、リラックスできません。
- 熱の放散不全と冷え 寒さや自律神経の乱れから、手足などの末端が冷え固まり、熱をうまく逃がせなくなります。深部体温が下がらないため、眠気が訪れず、布団の中で悶々としてしまいます。
これが、布団に入ってもなかなか寝付けない入眠障害の典型的なメカニズムです。
「入眠障害」とは?
入眠障害を改善するには、自律神経のバランスを整えることと、スムーズな体温調節ができるように体を温めることが重要です。
当院で行う箱灸は、腹部と腰仙部(お腹と腰の下側)を温めることで、これらの課題に集中的にアプローチします。
理由① 腹部の温熱で「内臓の緊張」をゆるめる
腹部には、多くの消化器官や、自律神経のネットワークが集中しています。
- 副交感神経の活性化 お腹に箱灸のじんわりとした心地よい温熱を与えることで、内臓の働きが安定し、休息モードである副交感神経の働きが優位になります。
- リラックス効果 腹部から伝わる深い温かさは、胃腸の緊張や過度な活動を穏やかに鎮め、心身の緊張を内側から解きほぐします。これにより、高ぶっていた交感神経が静まり、スムーズな入眠に必要なリラックス状態へと導かれます。
理由② 腰仙部の加温で「冷え」を根本から対策
腰仙部(骨盤の中央から下側)は、冷えの影響を受けやすく、また血流が集まる重要な部位です。
- 血行促進による放熱サポート 腰仙部を温めることで、下半身全体の血流が良くなります。この血流改善により、全身、特に手足の末端まで温かい血液が巡りやすくなります。入眠に必要な「手足から熱を放散する働き」がスムーズになり、深部体温が下がりやすくなることで、自然な眠気を誘います。
- 体の土台から冷えを改善 11月下旬にかけて冷え込むにつれて、腰や足元からの冷えは入眠を妨げます。箱灸は、この体の土台となる部位を深部から温め、冷えからくる体の無意識の緊張を取り去る効果があります。
理由③ 継続的な刺激による「体質の安定化」
単なる一時的な温めではなく、箱灸による継続的な温熱刺激は、自律神経の働きを安定させ、体質そのものを改善します。
施術を重ねることで、「夜になると自然と体がリラックスモードに切り替わる」という正しいリズムを体が思い出し、寒暖差やストレスがあっても影響を受けにくい快眠体質へと近づくことができます。
自宅でできる入眠のための簡単セルフケア
お灸の施術と合わせて、ご自宅でも入眠をサポートする工夫をしてみましょう。
- 就寝前の「光」の調整 眠る1時間前からは、スマートフォンやパソコンの画面を見るのは避けましょう。ブルーライトは脳を興奮させ、交感神経を刺激してしまいます。照明も暖色系の間接照明に切り替えましょう。
- 寝具の工夫で冷えを防ぐ 11月は急に冷え込むため、特に首元、足元、腹部の保温を意識しましょう。湯たんぽや腹巻、厚手の靴下(寝る直前には脱ぐなど調整)などを活用し、寒さによる体の緊張を防ぎましょう。
- 就寝前のリラックスタイム ぬるめのお湯にゆっくり浸かる、軽いストレッチや深呼吸をするなど、自分なりの方法で意識的に副交感神経を優位にする時間を確保しましょう。
心地よい温かさで入眠の壁を乗り越える
11月の「寒暖差」は、自律神経のバランスを崩し、多くの方の寝つき(入眠)に影響を及ぼしています。
この季節の変わり目を健やかに乗り越え、毎日ぐっすり眠るためには、乱れた自律神経のバランスを整え、冷えによる体の緊張を解きほぐすことが大切です。
当院の箱灸は、腹部と腰仙部への心地よい温熱で、体の内側からリラックスを促し、スムーズな体温調節をサポートします。
「寝つきの悪さを何とかしたい」「翌朝スッキリ目覚めたい」とお考えの方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
注:本記事は入眠障害の改善を保証するものではありません。症状が重い場合は専門医にご相談ください。