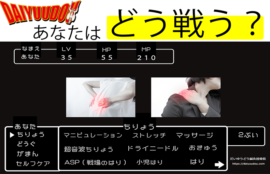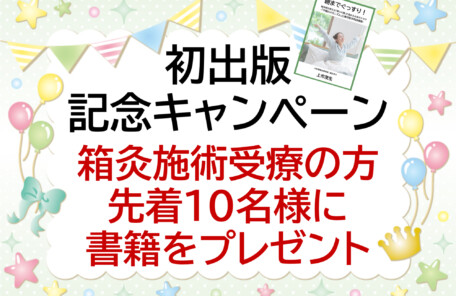「最近、うちの子が膝の下を痛がるんだけど、成長痛かしら?」成長期のお子さんをお持ちの親御さんにとって、子どもの訴える痛みは心配の種ですよね。特に、活発に運動するお子さんの場合、膝の痛みを「成長痛」と安易に考えてしまうことがあるかもしれません。
しかし、膝の下の痛みの場合、成長痛と非常によく似た症状を示す「オスグッド・シュラッター病(以下、オスグッド病)」である可能性があります。この二つは全く異なる病態を持つため、正しく理解することが大切です。
この記事では、オスグッド病がなぜ成長痛と誤認されやすいのか、その病態に焦点を当て、一般の方にも分かりやすく解説します。医学文献を参考に、その違いを明確にしていきましょう。

なぜオスグッド病は成長痛と間違われやすいのか?
オスグッド病と成長痛が混同されやすいのには、いくつかの理由が考えられます。
・好発年齢が近い
どちらも成長期、特に小学生高学年から中学生にかけて起こりやすいです。
・運動後に痛みが出やすい
活発な子どもに多く、運動後に痛みを訴えることが多いという共通点があります。
・一時的な痛みと考えられがち
どちらも、安静にしていれば痛みが軽減することがあります。
しかし、これらの共通点がある一方で、痛む場所や体の内部で起こっていることは大きく異なります。
成長痛とは?(比較のために解説します)
一般的に「成長痛」と呼ばれる痛みは、特定の場所がはっきりとせず、筋肉痛のような漠然とした痛みを訴えることが多いです。夕方から夜にかけて、両足のすねや太ももの裏などが痛むことが多く、朝には痛みが消えていることが多いとされています。成長痛の原因は、骨の急な成長に筋肉や神経の成長が追いつかないために起こると考えられていますが、明確な病態はまだ完全に解明されていません。
オスグッド病の病態:成長痛との明確な違い
オスグッド病は、成長痛とは異なり、明確な病態と痛む場所を持ちます。その核心となるのは、膝のお皿の下にある「脛骨粗面(けいこつそめん)」と呼ばれる骨の突起部分で起こる炎症と、それに伴う骨の変化です。
1.痛む場所が明確
オスグッド病では、ほぼ例外なく脛骨粗面という一点にピンポイントで痛みが生じます。押すと強い痛みがあり、場合によっては腫れや熱感を伴うこともあります。成長痛のように、広範囲にわたる漠然とした痛みではありません。
2.繰り返される牽引力による負荷
オスグッド病の主な原因は、太ももの前側の筋肉である大腿四頭筋の強い収縮です。大腿四頭筋は膝を伸ばす際に働き、その腱は脛骨粗面に付着しています。ジャンプやダッシュ、ボールを蹴るなどの動作を繰り返すことで、この腱が脛骨粗面を強く引っ張り、まだ成長軟骨が残る未熟な脛骨粗面に微細な損傷を引き起こします。
3.骨の隆起(進行した場合)
オスグッド病が進行すると、脛骨粗面が徐々に盛り上がってくることがあります。これは、体が損傷部位を修復しようとする過程で、軟骨の一部が骨に置き換わる骨化や、炎症による骨の反応が起こるためです。成長痛では、このような骨の隆起は見られません。
4.成長軟骨の関与
成長期の子どもの骨には、「骨端線」と呼ばれる成長のための軟骨組織が存在します。脛骨粗面もこの骨端線の一部であり、まだ完全に硬い骨になっていません。大腿四頭筋の強い牽引力は、この脆弱な成長軟骨に特に負担をかけやすく、オスグッド病の発症につながります。成長痛は、骨の成長そのものが原因と考えられていますが、特定の成長軟骨の損傷が直接的な原因ではありません。
自己判断せずに専門医の診断を
オスグッド病は、成長痛と症状が似ている部分もありますが、痛む場所、発症のメカニズム、そして体の内部で起こっていることは明確に異なります。特に、膝の下の特定の場所が痛む、運動後に痛みが強くなる、押すと強い痛みがあるといった症状が見られる場合は、自己判断せずに整形外科などの専門医を受診し、正確な診断を受けることが重要です。適切な診断と、その後の適切な対応が、お子さんの健やかな成長をサポートする上で不可欠となります。
参考文献
日本整形外科学会. (2017). 整形外科診療ガイドライン 2017. 南江堂.