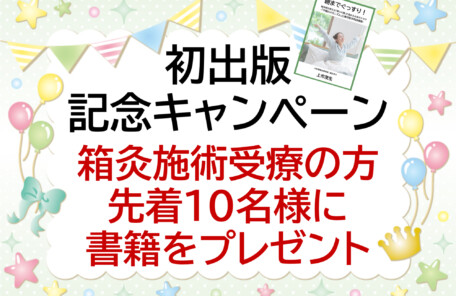成長期のお子さんが膝の下の痛みを訴える場合、オスグッド・シュラッター病(以下、オスグッド病)の可能性があります。スポーツをする活発なお子さんに多く見られるこの疾患に対して、整形外科ではどのような治療が行われるのでしょうか?
この記事では、オスグッド病と診断されたお子さんに対して、整形外科で一般的に行われる標準的な治療法について、保護者の皆様にも分かりやすく解説します。

オスグッド病に対する整形外科的治療の基本方針
オスグッド病の治療は、基本的に手術を必要としない保存療法が中心となります。成長期の一過性の疾患であり、多くの場合、成長とともに自然に症状が軽減していくため、痛みをコントロールし、日常生活やスポーツ活動への影響を最小限に抑えることが主な目的となります。
1.安静
痛みが強い時期には、まず運動を休止することが重要です。特に、ジャンプやダッシュ、ボールを蹴るなど、膝に負担のかかる動作は避けるように指示されます。運動の種類や程度については、医師が症状の程度やスポーツの種類などを考慮して判断します。ただし、「完全に運動禁止」となるケースは少なく、痛みの程度に合わせて運動量を調整したり、膝への負担が少ない運動に切り替えたりするなどの指導が行われることが一般的です。
2.アイシング
運動後や痛みが強い時には、炎症を抑えるために患部を冷やします。冷却シートや氷嚢などを使い、1回15分程度を目安にアイシングを行います。直接皮膚に氷を当てると凍傷の危険があるため、タオルなどで包んで使用するように指導されます。
3.ストレッチング
大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)やハムストリングス(太ももの裏側の筋肉)など、膝関節に関わる筋肉の柔軟性を高めることは、オスグッド病の治療において非常に重要です。筋肉の柔軟性が低下すると、膝への負担が増加し、痛みを悪化させる可能性があるためです。整形外科では、適切なストレッチの方法やタイミングについて指導が行われます。運動前後のウォーミングアップやクールダウン時、入浴後などに行うことが推奨されます。
4.サポーター・装具療法
痛みが強い場合や、運動時に膝の安定性を高めるために、サポーターや装具が用いられることがあります。オスグッド病専用のサポーターや、膝全体をサポートするタイプのサポーターなど、症状に合わせて適切なものが選択されます。サポーターや装具は、痛みを軽減する効果はありますが、依存しすぎると筋力低下を招く可能性があるため、医師や理学療法士の指示に従って適切に使用することが重要です。
5.薬物療法
痛みが非常に強い場合には、炎症を抑えるために非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の内服薬や外用薬が処方されることがあります。これらの薬は、一時的に痛みを和らげる効果はありますが、オスグッド病の根本的な治療法ではありません。医師の指示に従い、症状に合わせて使用されます。
6.理学療法
痛みが慢性化している場合や、運動復帰を目指す場合には、理学療法が行われることがあります。理学療法士は、患者さんの状態に合わせて、ストレッチングや筋力トレーニング、関節の可動域改善訓練などの運動療法を行います。特に、大腿四頭筋の柔軟性改善や、膝関節周囲の筋力強化は、オスグッド病の症状改善や再発予防に重要とされています。
手術療法について
オスグッド病に対して手術が行われることは、非常に稀です。ほとんどの場合、成長とともに症状が自然に改善するため、手術が必要となるケースは限られています。手術が検討されるのは、成長期が終了しても痛みが強く日常生活に支障をきたすような場合に、骨化した脛骨粗面の隆起を摘出するなどの処置が行われることがあります。しかし、これは最終的な選択肢であり、まずは保存療法が徹底的に行われます。
治療期間と運動復帰
オスグッド病の治療期間は、症状の程度や個人の回復力によって異なります。数ヶ月で痛みが軽減するお子さんもいれば、成長期が終わるまで症状が続くお子さんもいます。運動への復帰時期は、痛みの程度や運動の種類、医師の判断によって異なります。痛みが完全に消失してからではなく、痛みをコントロールしながら徐々に運動量を増やしていくことが多いです。
保護者の皆様へ
お子さんがオスグッド病と診断された場合、保護者の方としては心配な気持ちになると思いますが、過度に悲観的になる必要はありません。整形外科医の指示に従い、適切な治療とケアを行うことで、多くのお子さんはスポーツ活動を続けながら成長期を乗り越えることができます。治療の過程で不安なことや疑問点があれば、遠慮せずに医師や理学療法士に相談するようにしてください。
参考文献
・日本整形外科学会. (2017). 整形外科診療ガイドライン 2017. 南江堂.
・日本臨床スポーツ医学会. (2018). スポーツ整形外科学. 文光堂.
・発育期におけるスポーツ障害の疫学. 体育の科学, 58(5), 349-355.
・成長期スポーツ障害の病態と理学療法. 理学療法学, 33(1), 1-9.