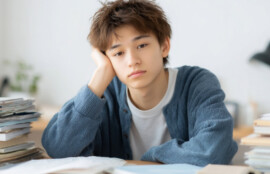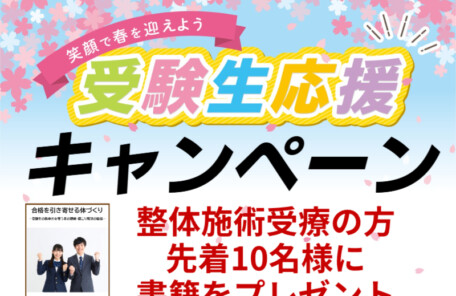第3回 実は見落としがち?季節の変わり目と自律神経の乱れが筋肉に与える影響
記録的な猛暑だった夏も終わりを告げ、ようやく涼しさが感じられる季節になりました。前回のブログでは、夏の間に鈍った身体で急に運動を再開することの危険性についてお話ししました。今回は、9月特有の気候が身体の内側に引き起こす「見えない変化」に焦点を当てていきたいと思います。
日中はまだ残暑が厳しいものの、朝晩はひんやりと肌寒さを感じる日が増えていませんか?この急な気温差こそが、肉離れを招く大きな要因の一つ。なぜなら、気温差は私たちの意思とは無関係に働く「自律神経」を乱し、筋肉の状態を悪化させるからです。
気温差が自律神経を乱すメカニズム
自律神経には、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」の二つがあります。この二つの神経がバランスを保ちながら、心拍数、血圧、呼吸、体温調節など、身体のあらゆる機能を自動的にコントロールしています。
9月になり日中と朝晩の気温差が大きくなると、身体は昼間の暑さに対応するために交感神経を活発にし、夜間の冷え込みに対応するために副交感神経を優位にしようと、常にバランスを切り替えようとします。この急激な切り替えは、自律神経に大きな負担をかけ、そのバランスが乱れやすくなります。
自律神経の乱れは、さまざまな身体の不調を引き起こしますが、筋肉に関わる最も大きな問題は「血行不良」です。
自律神経の乱れが引き起こす血行不良と筋肉の硬直
自律神経は、血管の収縮・拡張もコントロールしています。通常、交感神経が優位になると血管は収縮し、副交感神経が優位になると血管は拡張します。
しかし、気温差で自律神経が乱れると、この血管の収縮・拡張がスムーズに行われなくなります。特に、交感神経が過剰に優位な状態が続くと、血管は常に収縮した状態になり、血液の流れが悪くなります。
血行不良が起きると、以下のような悪循環が生まれます。
- 酸素と栄養の不足 血液は、筋肉に酸素や栄養を運ぶ役割を担っています。血行が悪くなると、筋肉に必要な栄養が届かず、筋肉細胞の活動が鈍くなります。
- 疲労物質の蓄積 同時に、筋肉から老廃物や疲労物質を排出する機能も低下します。乳酸などの疲労物質が筋肉内に溜まり続けることで、筋肉は硬く、こわばった状態になってしまいます。症状 「ふくらはぎをバットで叩かれたような」突然の激しい痛み。
この状態の筋肉は、柔軟性や弾力性を失い、まるでゴムが劣化したようなもろい状態です。このような筋肉は、少し無理な負荷がかかっただけで、簡単に断裂してしまい、肉離れを引き起こすリスクが非常に高くなります。
自律神経を整え、肉離れを予防する生活習慣
自律神経の乱れを整えるためには、日々の生活習慣を見直すことが最も重要です。
1.質の良い睡眠を確保する
睡眠は、自律神経を整え、身体の疲労を回復させる最も大切な時間です。就寝前はスマートフォンやパソコンの使用を控え、リラックスできる時間を作りましょう。
2.ぬるめのお湯にゆっくり浸かる
38〜40℃程度のぬるめのお湯に20分ほどゆっくり浸かることで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。血行も促進され、筋肉のこわばりを和らげる効果も期待できます。
3. こまめな水分摂取を徹底する
自律神経を整えるには、体内の水分バランスを保つことが不可欠です。水分不足は血液をドロドロにし、血行不良をさらに悪化させます。喉が渇いたと感じる前に、こまめに水分を摂る習慣をつけましょう。特に起床時や入浴前後は、脱水状態になりやすいので意識して水分を補給してください。
大有堂鍼灸接骨院から皆さまへ
9月の肉離れは、単に運動不足だけでなく、身体の内側で起きている自律神経の乱れも大きな原因です。ご自身の身体が「硬い」「重い」「なかなか疲れが取れない」と感じることは、自律神経のSOSかもしれません。
「自律神経のバランスを整えたい」「身体の根本から改善したい」とお考えの方は、ぜひ当院にご相談ください。
当院では、単なるマッサージではない、「全身調整」を通じて、自律神経のバランスを整え、血行を促進することで、肉離れが起きにくい「しなやかな身体」作りをサポートします。
次回の予告
第4回の記事では、「もし肉離れが起きてしまった場合の、正しい応急処置と、その後の適切な専門的ケア」について詳しく解説していきます。どうぞお楽しみに!